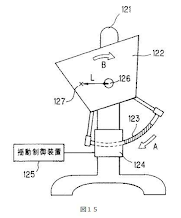2023年7月6日木曜日
[裁判例]均等論の枠組み(令和3年(ワ)10032号)
2022年3月27日日曜日
[裁判例]遠隔監視方法事件(知財高裁令和3年11月25日)
2021年8月26日木曜日
[均等論]半導体チップの製造方法事件(東京地裁平成28年10月14日)
2021年8月23日月曜日
[均等論]ナビゲーション事件(知財高裁 平成29年5月23日)
2021年8月22日日曜日
[均等論]骨の固定手段装置(知財高裁 平成29年12月5日)
2021年8月21日土曜日
[均等論]導光板事件(知財高裁 令和元年7月10日)
2021年8月20日金曜日
[均等論]生活地図事件(知財高裁 令和元年7月19日)
2021年8月17日火曜日
[均等論]美容器事件(知財高裁令和3年3月8日)
2021年8月16日月曜日
[均等論]振動機能付き椅子事件(知財高裁平成28年6月29日)
2021年8月15日日曜日
[均等論]情報端末サービスシステム事件(知財高裁 平成30年6月19日)
2021年8月14日土曜日
[均等論]人脈関係登録システム(知財高裁令和元年9月11日)
2021年4月7日水曜日
[裁判例]学習用具事件(大阪地裁令和3年3月25日)
2020年7月21日火曜日
均等論について ~電子メール誤送信防止事件の補足~
2020年7月15日水曜日
[裁判例]電子メール誤送信防止事件(知財高裁 令和2年6月18日)
本件は、電子メール誤送信防止に関する特許権を保有するキャノンITソリューションズがデジタルアーツ株式会社を訴えた事件の控訴審である。
対象となる特許は、電子メールを送信する際に、メールの誤送信を防止するために、送信先と送信元に対応付けた制御ルールに基づいて、メール送信を保留する技術に関する。この特許の特徴は、電子メールを複数の送信先に一斉送信するときに、送信先を個々の送信先に分割し、送信先ごとにメール送信を保留するか否かの判定を行うことにした点である。従来は、保留するかどうかの判定がメッセージ単位で行われていたため、一つでも保留条件を満たす送信先が含まれていると、その他のメール送信まで保留、取消がされるという課題があったが、本件発明はこのような課題を解決した。
これに対し、被控訴人の装置は、複数の宛先の電子メールアドレスが設定された電子メールを、宛先のドメイン毎の電子メールに分割するものである。
ドメインを特定するのみでは電子メールは受信者に届かないことや、本件明細書の記載等から、上記要件における「送信先」は電子メールアドレスと解すべきであるとされた。この解釈を前提として、被控訴人の装置は、文言上、本件特許を侵害しないと判断された。「送信先」という文言からみても、妥当な判断である。
本件では、均等侵害についても判断されており、こちらの方が興味深い。
本件発明の課題は、次のとおりである。
「【課題が解決しようとする課題】
しかしながら、特許文献1に記載の技術においては、送信メール保留装置は受信したメッセージ単位でしか保留の可否を判断することができない。そのため、複数の送信先が記載された電子メールに対しては、誤送信の可能性がある送信先が1つでも含まれていれば、その他の送信先に対するメール送信までもが保留、取り消しがされることとなる。」
これに対して、裁判所は次のように判断した。
[裁判所の判断]
「特許文献1に記載の技術においては、送信メール保留装置は受信したメッセージ単位でしか保留の可否を判断することができない。そのため、複数の送信先が記載された電子メールに対しては、誤送信の可能性がある送信先が1つでも含まれていれば、その他の送信先に対するメール送信までもが保留、取り消しがされることとなる。」(段落【0004】)とあるところ、一部であっても本来保留される必要のない送信先に対するメール送信が保留されれば、誤送信の可能性がある送信先が1つでも含まれていることにより、メール送信が保留されてしまったことに変わりはないから、本件発明1の課題は、誤送信の可能性がないその他の送信先に対するメール送信は保留、取り消しがされなくなることと解すべきであり、メッセージ単位での保留の可否判断よりも送出制御を効率化すれば足りるとはいえない。
という判断を元に、
・・・(段落【0004】①)とは、本来保留される必要のないその他の送信先(すなわち電子メールアドレス)に対するメール送信は全てなされるべきであるとの趣旨と解するのが自然である。
また、前記アのとおり、「効率よく電子メールを送出させる」ことは、電子メールアドレスに応じた電子メールの送出制御によってもたらされるものとされている。電子メールアドレスに応じた電子メールの送出制御によれば、保留の必要がないその他の電子メールアドレスに対する送信は全てなされるのであるから、本件発明の効果も同様と解すべきであって、保留の必要がないその他の電子メールアドレスのうちの一部の電子メールアドレスに対する電子メールの送信が保留されなくなることでは足りないというべきである。
この点に関して、控訴人の主張も主張しており、それに対する裁判所の判断は次のとおりである。
[裁判所の判断]
ウ 控訴人は、文言侵害が否定された場合に、本件明細書等1の課題に記載された「送信先」を「電子メールアドレス」と読み替えて、課題を認定し、当該課題から直接的に本質的部分を認定することは、均等侵害の成否の場面において、文言侵害が否定されることを理由に、均等侵害の成立が直ちに否定され、均等侵害がその機能を果たさない結果となることから、かかる結果が著しく妥当性を欠く旨主張する。
しかし、本質的部分の認定は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである(大合議判決)。よって、本件明細書等1の記載に基づいて、本件発明1が、従来技術である特許文献1のどのような点を課題として把握し、どのような解決手段を提示し、どのような効果をもたらすものなのかを把握することは、当然なされるべきことであるから、控訴人の主張は理由がない。
このような判示をみると、発明の課題はなるべく書かない方が得策なのかもしれない。書いていない分には、大合議判決(平成27年(ネ)10014号)のように、従来技術との対比によって、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定され、従来技術との差分が発明の本質的部分として認められる可能性があるからである。そして、後から差分を主張する方が、被疑侵害品が見えているだけにやりやすい。
除くクレーム(令和6年(行ケ)第10081号)
1 除くクレームについて 特許実務において、引用文献と差別化を図るために、構成要件の一部を除くことが行われることがある。新たな技術的事項を導入しないものである場合には構成要件の一部を除くことが認められるが(ソルダーレジスト大合議事件(平成18年(行ケ)第10563号))、...

-
米国における特許審査では、クレームは「最も広範な合理的解釈(BRI: Broadest Reasonable Interpretation)」のもとで解釈される。クレームが条件付き制限事項を含む場合のBRIについてMPEP2111.04 Ⅱに解説がある。 https://...
-
侵害鑑定を行う場合、通常は、独立項が非侵害ならばその従属項も非侵害と結論する。なぜなら、従属項は独立項の構成要件をそっくりそのまま備えているから、独立項において非充足の要件があれば従属項もその非充足の要件を備えているからである。 思考実験として、均等侵害の場合について考えてみ...
-
特許が有効であるとした無効審判の審決に対する審決取消訴訟である。無効理由は、分割要件違反を前提とする新規性・進歩性欠如、分割要件を前提としない進歩性欠如、補正要件違反、サポート要件違反、明確性違反と多岐にわたるが、特許庁はすべての理由が成り立たないとした。裁判所はサポート要件に...